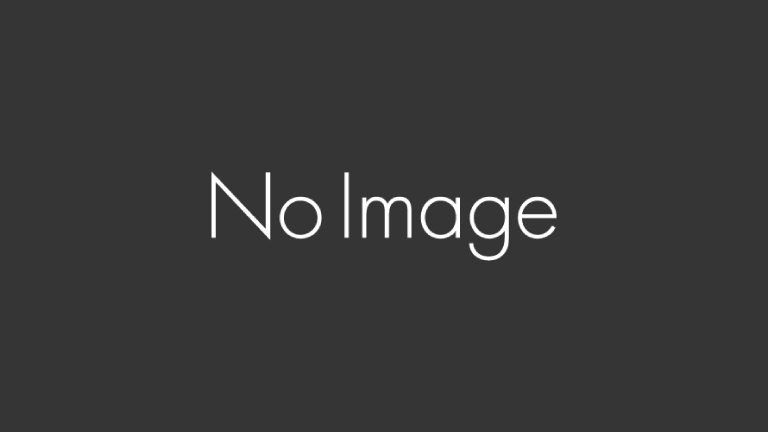文鳥は見た目がかわいいだけでなく、鳴き声も魅力的です。
人になつきやすく、家で飼うのに向いているペットとして知られています。
しかし、犬や猫に比べると、文鳥の情報が少ないため、興味があっても飼い始めるのをためらう人も少なくありません。
文鳥を飼う際のお世話はどれくらい難しいのでしょうか?
また、文鳥の寿命や飼育にかかる費用はどれくらいなのか気になりますよね。
そんな疑問を持つ方々に向けて、文鳥の飼い主である私が、文鳥の特性やお世話の仕方、飼育で苦労した経験を分かりやすく解説していきます!
文鳥に関する基本情報
まずは、文鳥に関する基本情報をまとめておきます。
基本的な知識を知っておかなければ飼育はできませんので、目を通しておきましょう。
文鳥ってどんな鳥?
文鳥はインドネシア原産のスズメ目に属する小さな鳥です。
スズメの一族であるフィンチ系の小鳥としても知られています。
フィンチ系の小鳥の見分け方は、意外に簡単です。特に嘴や足の形、そして歩き方に注目するといいでしょう。
嘴は真っ直ぐで先端が尖っており、これは種子や虫をついばむのに適しています。
足は前に3本、後ろに1本の指があり、この足でぴょんぴょんと跳ねる歩き方が可愛らしいです。
文鳥の体長は成鳥で約15cm、体重は約25gと手のひらサイズで非常にコンパクトです。
体重が30gを超えると肥満とみなされ、人間と同じように健康を守るためにダイエットが必要になることもあります。
文鳥はどんな性格?
文鳥は感情が豊かな鳥で、好きな相手にはたくさん甘えたり、尽くしたりする一方で、苦手な相手には威嚇したり、時には噛みつくこともあります。
さらに、文鳥は寂しがり屋の性格を持っていて、一人でいることが多いと、寂しさからストレスを感じて自分の羽をかじってしまうことがあります。
文鳥の特徴は個体によっても異なりますが、オスとメスでは性格が異なることもあります。
オスは活動的でやんちゃな性格が多く、求愛のダンスや歌で積極的にアピールすることが特徴です。
意外にも新しいおもちゃなどには警戒心を持つことが多いです。
一方、メスはもっと穏やかでマイペース。
好奇心が強く、新しいものに対して興味を示すことが多いです。
寿命は長い?
文鳥の寿命は通常7~8年とされていますが、飼育環境によって大きく異なることがあります。
特にオスはメスよりも長生きする傾向がありますが、これはメスの産卵に関連しています。
メスの文鳥が卵を産む際には体に大きな負担がかかります。
特に「卵詰まり」という状態になると、これが直接命にかかわることもあります。
一匹だけで飼育していても、メスの文鳥は人間をパートナーと認識して発情し、無精卵を産むことがあります。
そのため、メスを飼う場合は発情を抑える対策が必要です。
このような対策を適切に行うことが、メスの文鳥を健康に長生きさせる秘訣となります。
文鳥の種類別解説
文鳥にはさまざまな色がありますが、主にペットショップで人気のあるいくつかの種類を紹介しますね。
まず、桜文鳥は黒と白の組み合わせが基本で、とても丈夫でなつきやすいため、小鳥を初めて飼う方にピッタリです。
次に、真っ白で美しい白文鳥は、明治時代に日本で生まれたと言われ、夏目漱石の小説にも出てくるほど歴史があります。
シルバー文鳥は薄いグレーが魅力的で、特に色素が薄い個体は「シルバーイノ」と呼ばれ、その希少な美しさで注目されています。
ブラウンカラーが温かみを感じさせるシナモン文鳥は、オランダ生まれとされています。
最後に、クリーム文鳥は、頭と羽は白っぽく、お腹は赤茶色です。
赤い目が印象的で、この赤い目は色素が薄いため、強い日差しは避けるようにしましょう。
購入・飼育にかかる費用
文鳥は種類や年齢によって価格が異なり、一般的には2,000円から10,000円の範囲で販売されています。
桜文鳥や白文鳥などは、比較的一般的な種類で、価格はだいたい5,000円前後です。
一方、シルバー文鳥やクリーム文鳥、シナモン文鳥などの希少な種類は、その珍しさから価格も高めです。
初めて文鳥を飼う際の初期費用としては、ゲージやペットヒーター、餌などの基本的なアイテムを揃えると、およそ1万円かかります。
月々の餌代は1匹あたり約500円程度です。
ただ、餌代以外にもいくつかの追加費用が発生します。
例えば、文鳥の健康管理のためには温度調整が必須なので、電気代が増えることを覚悟しなければなりません。
特に、人間には快適な気温でも、文鳥のためにエアコンやヒーターを使うことが多いです。
消耗品代としては、文鳥のトイレトレーニングが難しいため、フンを片付けるために大量の紙が必要です。
また、病院代も考慮する必要があります。
文鳥が病気になった時だけでなく、定期的な健康診断や爪切りのために病院に行くこともあります。
これらの費用もある程度見込んでおくと良いでしょう。
文鳥の飼い方
続いて、文鳥の飼い方についてご説明していきます。
お世話の仕方を把握しておかないと、飼ってから後悔しても遅いです。
あらかじめ確認しておきましょう。
餌はどうする?
生まれたばかりのヒナは、まだ自分で餌を食べることができないため、挿し餌が必要です。
ヒナ用のパウダーフードにぬるま湯を混ぜ、給餌器を使ってヒナの口に直接餌を流し込みます。
ヒナの小さい間は、2時間ごとにこの作業を繰り返す必要があります。
そのため、日中家にいることが難しい一人暮らしの方は、自分で餌を食べられる成鳥の文鳥を迎えることをお勧めします。
成鳥になると、フィンチ用のペレットや混合シードなどを主食として与えます。
これらの餌は、毎日新鮮なものに取り替えてあげることが大切です。
シードを主食とする場合、栄養バランスを考えて野菜などの副菜も併せて与えることが重要です。
このようにして文鳥の健康を支えてあげましょう。
放鳥時間の確保
文鳥を放鳥する時間は、鳥にとっても飼い主にとっても楽しいひとときです。
人間と同じように、文鳥も健康を保つためには運動が必要です。
だから、毎日最低でも30分は文鳥が自由に飛び回れる時間を作ってあげることが大切です。
水浴びが必須
文鳥は清潔を好む鳥です。羽をきれいに保つためには水浴びがとても重要です。
そのため、文鳥のゲージには水浴び器を設置するか、放鳥時に水浴びをさせてあげるようにしましょう。
お掃除も欠かせない
文鳥のゲージや止まり木、おもちゃは、週に一度から月に一度の頻度で水洗いをしましょう。
さらに熱湯で消毒し、天日干しにすることで菌の繁殖を抑え、清潔を保つことができます。
ゲージの中にはフンが溜まりやすいので、フン切り網は毎日の掃除が必要です。
ゲージの底に敷紙を使う場合は、毎日新しいものに交換しましょう。
また、水飲み器や水浴び器、餌入れも毎日水で洗って、常に清潔な状態を保つことが大切です。
温度・湿度をキープする
文鳥の健康を守るためには、温度管理がとても重要です。
成鳥の場合は、室温を20~25℃、湿度を50~60%に保つようにエアコンやペットヒーター、加湿器を使って調整します。
一方、ヒナの場合は体を温めるのに適した温度が30℃です。
ヒナを保温するためには、プラスチックケースにヒーターを設置して、ちょうど良い温度を保つ必要があります。
このように、文鳥の年齢に応じて適切な温度管理を行うことが、健康維持には欠かせません。
文鳥を飼って大変だったことをランキング形式で紹介
私が実際に文鳥を飼ってみて、大変だったなと思った順にランキング形式でご紹介します。
とっても愛らしい反面、やはり生き物なので、飼ってみてお世話を辛く感じることもありましたので正直にお伝えしますね。
飼い主になつき過ぎて離れてくれない
文鳥は非常に愛情深く、寂しがり屋な鳥です。
放鳥すると、飼い主のそばから離れようとしないほどです。
幼鳥の頃から育てると、文鳥は人の手を非常に好むようになります。
それは、手の上で安心して眠ってしまうほど。
これにより、自分の趣味や家事を後回しにしなければならないこともあり、一日中何もできないことがあるかもしれません。
私にとってはこれが幸せに感じる瞬間なのですが、中にはストレスを感じる人もいるかもしれませんね。
さらに、文鳥がゲージの中にいるときであっても、懐き過ぎて「出してほしい」と強く鳴いてアピールすることも。
そのため、文鳥がいる環境でのテレワークはかなり困難でした。
通える病院を探しておく
犬や猫を診る病院はたくさんありますが、小鳥を診てくれる病院は意外に少ないです。
小鳥の診察を行っているところでも、鳥を専門にしていないため、適切な処置ができなかったり、間違った診断を受けることもあります。
私も以前、文鳥が怪我をしたときに、信頼できる病院を見つけるのが大変で、結果的に文鳥にとってつらい経験となってしまいました。
そのため、文鳥を飼うことを考えている方は、事前に小鳥を診てくれる病院を探しておくことを強くお勧めします。
意外と難しいのが爪切り
文鳥の爪切りは、飼い主にとっても文鳥にとっても気が重い作業です。
多くの文鳥が爪切りを恐れ、その際に暴れるため、爪切り中に文鳥を抑えるのは非常に大変です。
爪切りを終えた後、文鳥が警戒して近寄らなくなることもありますし、もし爪を切り過ぎてしまうと出血し、場合によっては命に関わることもあります。
しかし、爪切りのためだけに毎回病院に行くのも、お金と時間がかかって大変です。
このように、文鳥を飼う人たちの中で、爪切りは共通の悩みの一つと言えます。
温度・湿度の管理が大変
文鳥の飼育において、適切な温度と湿度を保つことは非常に重要ですが、実際にはこれが想像以上に難しい作業です。
冬場に暖房を使うと室内が乾燥し、湿度が下がりすぎてしまうことがあります。
また、夏にエアコンで冷やすと、今度は冷えすぎることもあります。
このように、文鳥のために室内の温度や湿度を適切に保つためには、常に注意を払い、調整を行う必要があります。
性格によっては、神経をすり減らす人がいるかもしれません。
トイレの問題
鳥はトイトレができないため、文鳥を放鳥するときは家中がフンだらけになることもあります。
特に、ゲージの中では問題ありませんが、放鳥したときには注意が必要です。
実際に私も、出勤前に服にフンをされたり、お風呂上がりに頭にフンをされた経験があります。
文鳥を飼う場合、フンに対してある程度寛容になることが必要です。
これを受け入れることができなければ、文鳥の飼育は難しいかもしれません。
文鳥は鳥の中では比較的飼いやすいが責任重大
文鳥は比較的飼いやすいとされていますが、病院を探したり、爪切りをすること、温度や湿度の管理、フンの問題など、注意しなければならない点も多くあります。
また、文鳥は人に懐きやすく愛情深いため、その愛らしさと同時に、日々のケアが大変だと感じることもあるでしょう。
文鳥を飼う場合は、自分の時間を彼らに捧げるくらいの覚悟が必要です。
文鳥も小さな命を持った大切な生き物です。
もし飼うことにしたら、最後まで責任を持って世話をし、楽しく幸せな生活を一緒に送ってくださいね。